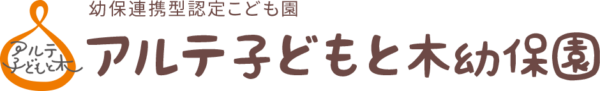コロナ禍の中で成長する子どもの姿 ☆発見
「おはよう」に 泣き顔の○○くん。 「なぜ 悲しいお顔をしているの?」
“マスクわすれた”と言いながら一人、友達の輪から離れています。
「そうか!困って涙が出るのね」に
“でもママが予備を入れてる”とカバンの中からマスクを取り出します。
「すごい、ママ用意してくれているんだ」に
“でもこれはいやだ”と泣きながら訴えます。予備のマスクは白い不燃紙のマスク、お気に入りのマスクでない。白いマスクに絵を描いてみたら等誘いますが “いやだ!!”
「じゃ、マスクしないで一人でいるの?」
「予備のマスクにする?」
○○くんが自分で決めてね。
しばらくして白のマスクをした○○くんの姿が。
次日、○○君の昨日の出来事を朝の集まりでお話します。小さなマスクの出来事でしたが○○君が自分でどちらにするか決めたこと・気持ちを切り替えられたことに成長を感じた出来事でした。みんなに拍手され笑顔の中に照れくさそう。
☆子どもへの声がけのポイント☆
秋は遠足の季節。電車等に乗ったら子どもに必ず「リュックを降ろしますか?どうしたい?」と問います。子どもは自分で判断、選択しなければなりません。
「私は降ろす。」「私は背負う。」迷っている子どももいます。こんな時は子どもに解るような情報を提供します。
この時保育士・保護者は「降ろしましょう。」・・・等々 大人の判断で指示せず子どもに考え決めさせるようにします。
一見、「降ろして。ここに置いていいよ」・・等々先回りして支持、やってあげることが、
とてもきめ細やかな保護者めんどうみの良い先生とみてしまうことが多いのですが
これでは子どもの自立を妨げてしまいます。小さなことの積み重ねが大事なのです。
指示され、やってもらうことに慣れすぎてしまうことのないようにしたいものです。