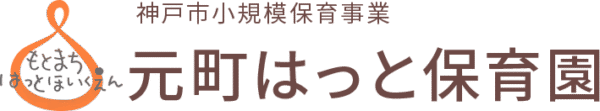活動ブログ
2021年9月21日~10月20日までの様子
2021年10月26日 火曜日カテゴリー: 園の取り組み
残暑が厳しい9月。まだまだ暑さをしのぎながらの活動となりました。お部屋の壁面の木もどんどん秋バージョンにリニューアルしていくために、造形あそびで壁面に使う土の部分をクレヨンでお絵描きしました。その上から絵具で塗り、はじき絵の土壌が出来ました。11月からお披露目します。お楽しみに。
また、秋空の中、運動会を行ないました。子ども達と職員のみの運動会ですが、とても楽しかったです。2歳児さんは一生懸命競技に参加し、1歳児さんは時々どこかにふら~っと脱走するのを「こっちよ~」と止められていました。また、外での食事も楽しかったです。保護者の方におにぎり弁当を作っていただき、持って行って食べたのですが、パクパク食べるスピードの速い事。あっという間に完食する子が続出。思ったよりも早く食べ終えたので、遊んで帰る余裕もありましたよ。
お散歩にも出かける日が増えました。心地よい秋の風に誘われるように、公園に行くと2歳児のかけっこが繰り広げられます。よーいどん!!と口走りながら、とても楽しそうですよ。
先月にさつまいもでクッキングを行いました。次はおいもスタンプをやってみました。もっと嫌がる子が出てくるかと思いましたが、みんなポンポンとたくさんスタンプし、ぶどうを作りました。個性豊かなぶどうが出来上がりましたよ(笑)。


ゴロンゴロン転がしました。



待て待て~!!

2021年8月21日~9月20日までの様子
2021年10月4日 月曜日カテゴリー: 園の取り組み
夏のあそびをたくさん楽しめた8月。 前半は雨が多く外で遊ぶことが少なかったのですが、後半は夏が回復してくれた為、水風船や色水あそびをすることが出来ました。 水風船は、初め「これなに?」と怪しい姿に遠巻きで見る子ども達。 でも職員が触ったり握って割ったりする様子を見ているうちに、「やる~」と近づいて来てキャーキャー言いながら触れていました。 また、色水あそびでは、色のグラデーションを楽しみました。 クレープ紙という紙を水につけるとその色が滲み出て、きれいな色水になります。 「コップにクレープ紙を1枚ずつ入れて作ってね」と言われてスタートしましたが・・・すぐに色水になるのが面白いようで、何枚も何枚も入れていきます。 そのせいで何とも言えない謎の色が出来ている子もいました。 2歳児の女の子は慎重に色を選び、大好きなピンク色を作ってうっとりしていましたよ。
8月末には洗濯あそびもしました。 石鹸で泡を作り、ままごとコーナーにある布のおもちゃやハンカチ、カバン、そして自分のTシャツを洗濯しました。 泡の中でゴシゴシ洗い、水でゆすいで干しました。 干すときに“パンパン”と叩いて干す子、一生懸命洗濯ばさみを付けようとする子など、お家の方の真似をしている(? )ような姿が見られました。
9月に入ってクッキングをしました。 今回は“いも餅”です。 サツマイモをマッシャーで順番にくずしていき、片栗粉を加えて混ぜ、一人ずつラップに包んで自分の分を丸めました。 ホットプレートに乗せて焼き、しょう油ベースのたれをつけて食べました。 素朴な味でしたが、子ども達は大喜び! 「おかわりください!」の声がたくさん出てきました。 また作りましょうね。

つんつん。 ぽよん、ぽよん。
もっともっと~!

おいしそうなジュース、出来るかな?

うわっ! なにこれ?

じゃぶじゃぶ。 あわあわ~。

ぺったん、ぺったん。

どう? これでいい?
2021年7月21日~8月20日までの様子
2021年8月17日 火曜日カテゴリー: 園の取り組み
暑い暑い夏がスタートしました。園では夏ならではの活動を増やしていきました。これで暑い夏を乗り切ろう~!!
<スイカ割り>
お家ではなかなかできないスイカ割りにもチャレンジしました。スイカ割りと聞くと目隠しをして棒を持ち、「右右!」「そこで叩く!!」などの周りからの声を頼りに行動するイメージでしょう。でも、子ども達はしっかり見えていてもなかなか叩けないものです。「そこで叩くよ」と言っても、「本当に叩いていいの?後で叱られるのでは?」というような顔をしていた子ども達。棒で突っついたり、恐る恐るふわっと叩いたりしながらも、何回も交代をしていく内に理解が出来たようです。すいかの頭が何となく柔らかくなった(何度もポコポコ叩いていたので…笑)頃、先生が「えい!」と最後の一振りで割りました。中身が見えると…子ども達の嬉しそうな顔!お皿にキレイに盛っていただきました。とても甘くておいしかったです。「またしようね」と子ども達からの声でしたよ。
<プールあそび&水あそび>
今年も園の商店街側にプールを設置してプール遊びを楽しみました。スタート時は水着に着替えることすら嫌がる子もいましたが、何度も遊ぶうちに自分から着替えの所に来るようにもなりました。また、メリケンパークの噴水にも行きました。大胆に濡れてもへっちゃらで、キャーキャー言いながら楽しんでいました。帰るのが嫌で泣くほど楽しんでいましたよ(笑)。
<大胆お絵かき>
模造紙を広げて、絵具であそびました。筆や手足でペタペタ塗っていきます。紙に塗っているのになぜか手足や顔にも絵具がついちゃいます。いつまでもペタペタ出来る子と、少し汚れたのを見てドン引きしてしなくなる子とに分かれました。感触あそびあるあるです。苦手な子も楽しめるアイデアを考えていこうと思います!!

えい!!え~い!!

みんなで食べたら美味しいね~!

わ~い!たのし~い‼

冷たくて!気持ちいいね!


見てみて~!
足にも手にもいっぱいつけたよ~!!

2021年6月21日~7月20日までの様子
2021年8月2日 月曜日カテゴリー: 園の取り組み
ようやく緊急事態宣言が解除され、まん延防止等重点措置に変更されました。世の中がちょっぴり動いたようですが、大喜びするにはまだ早いです。少しでも早く以前のような生活を取り戻せたらなぁと思いますが、それはかなり先の事になりそうなので、今は上手にこの環境と共存しつつ、そんな中でも楽しい事探しをしていこうと思います。
夏ならではのあそびをどんどん進めていっています。寒天あそびでは、冷たくひやした寒天の感触が楽しくて子どもたちは大喜び!!はじめは指でツンツンと突いて様子を見ていましたが、最後は大胆にモミモミしていました。
今年度初めての“おたのしみライブ”が行なわれました。今回は職員のMさんに依頼してフルートの演奏をしてもらいました。子どもたちはもちろん、通りかかった方々も足を止めて演奏に聞き入っていました。中には、「次の公演はいつありますか?予約はできますか?」と質問されたほど大盛況で、本当に素敵な演奏でした。
フロリーナを氷の中に入れて凍らせ、子ども達とこすって溶かすと中のおもちゃをゲットできるあそびをしました。みんな不思議そうにキュッキュッとこすっていましたが、「つめた~い!」と言いながらも、一生懸命溶かしていました。夏ならではのあそびですね。

プルンプルンで気持ちいいなぁ♪

一緒に歌って楽しんだよ。

優しく触ってみよう。

バシャバシャ楽しいな~。

冷たいけど、触りたーい!

泥の感触にハマってます。
2021年5月21日~6月20日までの様子
2021年6月30日 水曜日カテゴリー: 園の取り組み
今年は梅雨入りが早かったので活動が予定通り出来るか心配しましたが、雨の日がそんなに続くこともなく良い加減で過ごせています。今年度は“食育”の観点から植栽を頑張っていこうと取組んでいます。自分達で育て、収穫したものをみんなで食すると、いつもは「嫌い!」と言って口にしない子でも、少しはチャレンジしてみようかな?という気持ちになってくれます。もちろん克服まではいかなくても、ペロっと口にしてくれるだけでも絶好のチャンスです。そんな部分も期待しながら現在、きゅうりとトマトを育てています。毎朝、「大きくなってね」とジョウロで水をあげていますので、きっと美味しい実がなってくれるでしょう。期待しながら毎日愛情をもって育てていこうと思います。
また、先日は商店街の八百屋さんにキャベツを買いに行き、持ち帰ってきました。みんなでキャベツを抱っこしたり匂いを嗅いだりしました。その後、ちぎってお湯にくぐらせ軽く塩をして食べてみました。キャベツの甘みを感じながら「美味しいね」という子ども達でした。

正解は・・トマト!

ふかふかの土になあれ。


おかね、どこに置くの?

わ!おもたい!